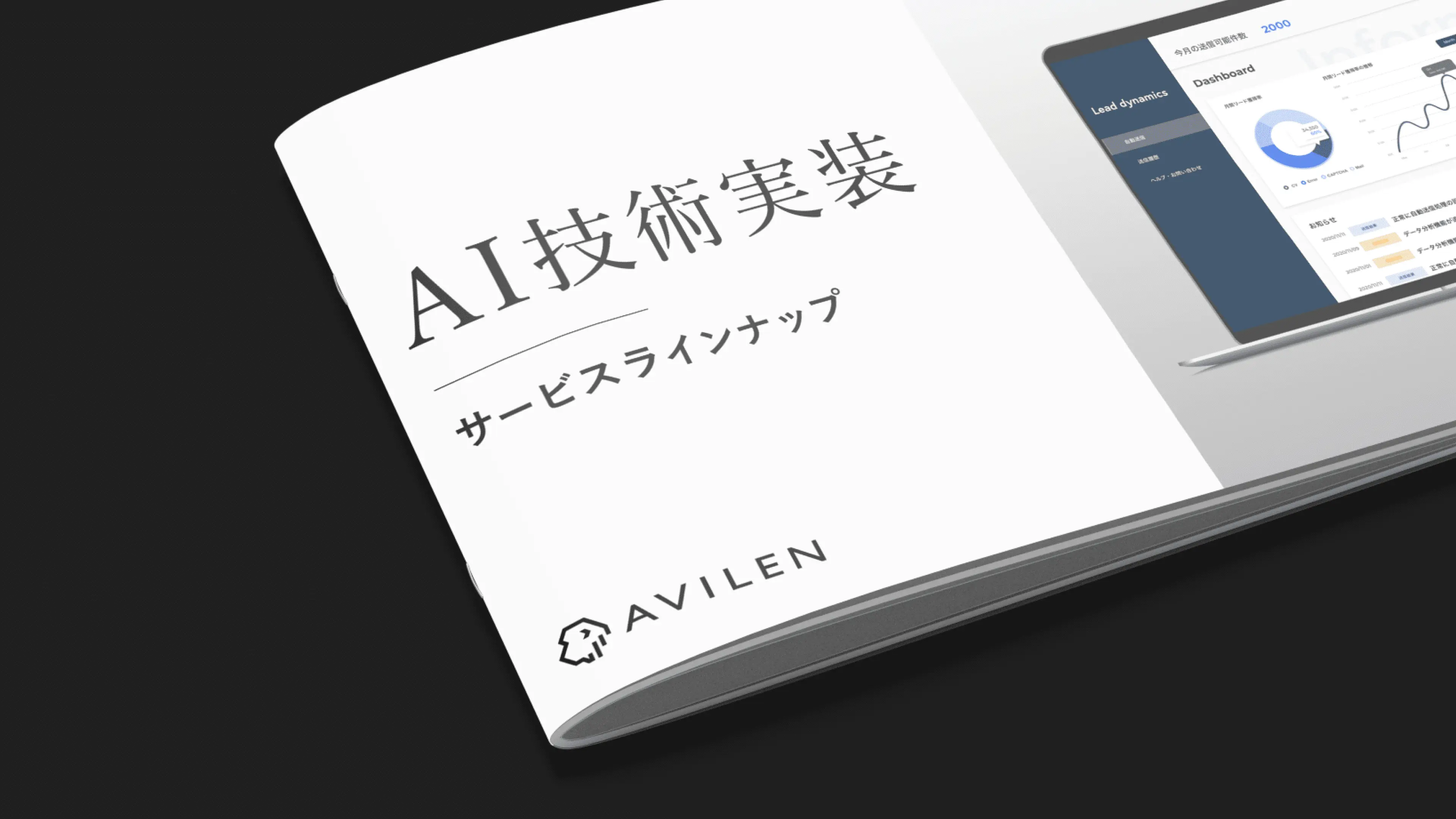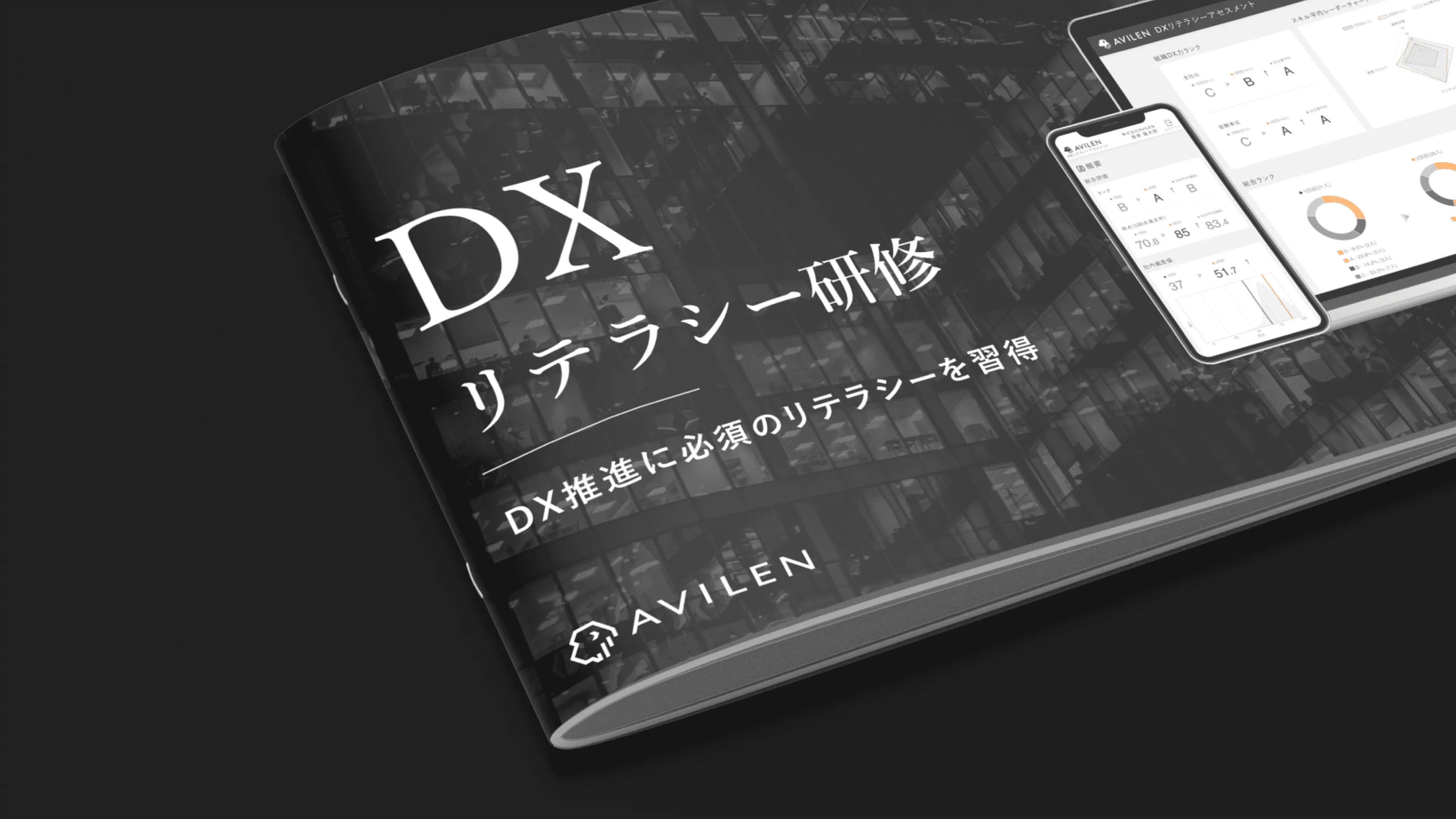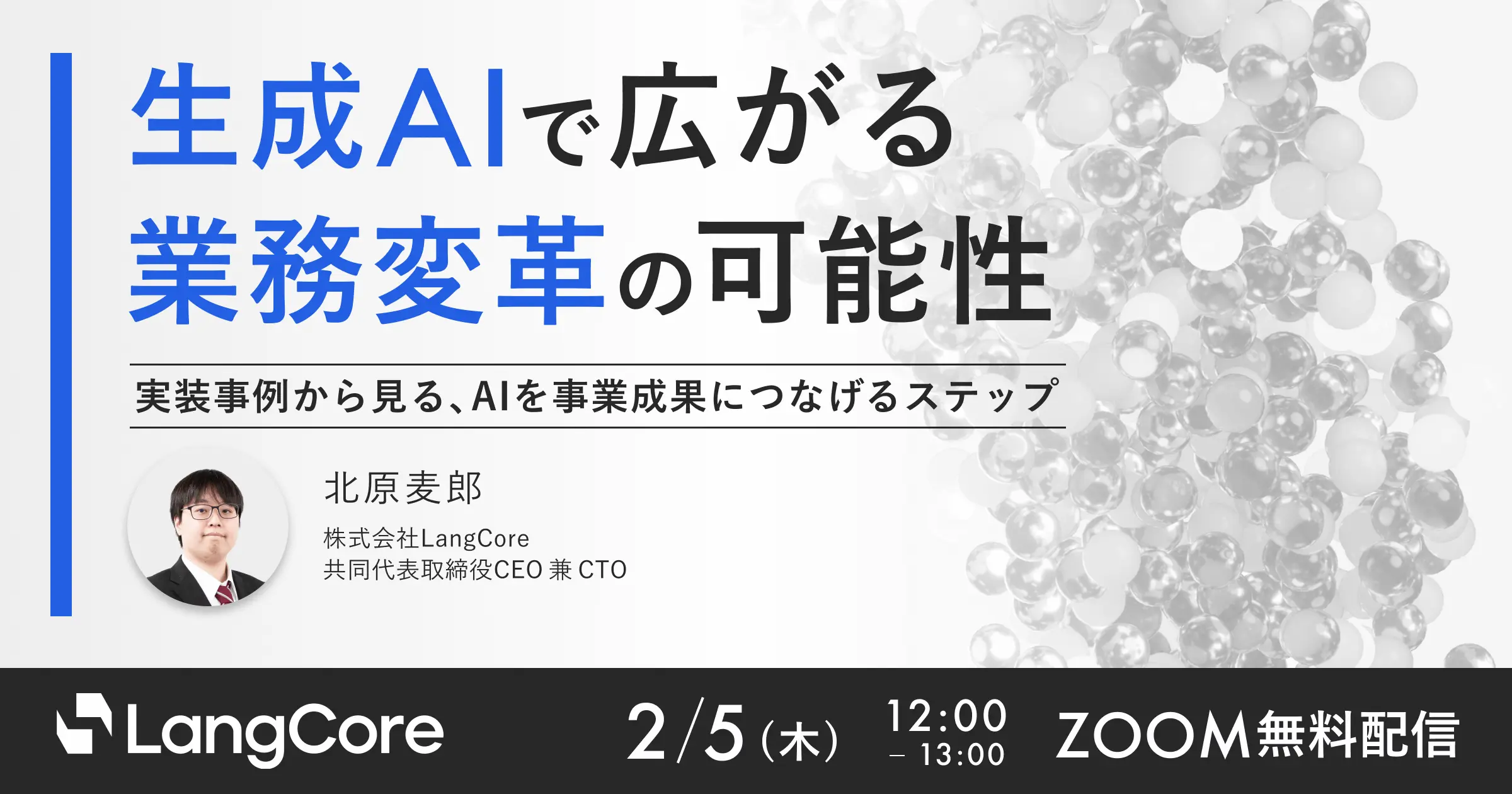本当に意味のある使い方を見出す。三菱UFJニコスが全社をあげて取り組む、生成AI活用キラーケース創出プロジェクト。

三菱UFJニコス株式会社は、生成AIの活用を通じた業務効率化・サービス向上を目指し、2024年4月より「生成AI活用キラーケース創出プロジェクト」を開始。生成AIの“業務特化”活用のあり方を模索し、社内活用の裾野を広げる取り組みを進めています。プロジェクトの背景や成果・今後の展望についてお話を伺いました。
【写真左から】寺木様(コミュニケーション推進部)/ 原様(事務企画部)/ 道家様(デジタル企画部)/ 白滝様(デジタル企画部)/ AVILEN 高橋
プロジェクトの狙いと概要
ー まずはどのような経緯で、「生成AI活用キラーケース創出プロジェクト」を実施することになったのでしょうか?
道家:
このプロジェクトを開始する少し前から『ChatMee*』を全社的に導入させていただき、生成AIを業務に活用し始めていた状況でした。翻訳や要約といった汎用的な活用が中心でしたが、次のステップとして、より深く入り込んだ "業務特化型" のユースケースを生み出したいという思いがありました。そこでAVILENさんに協力いただきながら、当社事業部の方々を巻き込んだ『アイデアソン』という形で進めていきました。
*ChatMee:AVILENが提供する法人向けChatGPT(https://avilen.co.jp/dev/saas/chatmee/)
デジタル企画部 道家様
白滝:
当社では、RPAや自動化ツールはこれまでも積極的に導入しており全社的にも活用が進んでいましたが、AI・特に生成AIに関してはインパクトのある活用方法をなかなか導き出せずにいました。“キラーケース”になり得る活用法・テーマを複数案創出し、効果的な活用の目処を立てるところまでが、本プロジェクトの目標でした。その中で特に効果的な活用法を見出すことができた部署が、寺木さんのコミュニケーション推進部と、原さんの事業企画部です。
デジタル企画部 白滝様
プロジェクトを通じて得られた成果
ー 今回のプロジェクトで、寺木さん、原さんの部署はそれぞれどのような活用法を見出せたのでしょうか?
寺木:
私たちコミュニケーション推進部では、コールセンター業務において、お客様が自己解決できる仕組みの構築が長年の課題でした。生成AIを活用することで、よりパーソナライズされた対応が可能になるのではないかと考え、具体的な検証を行いました。
コールセンター業務のAI化において忘れてはいけないのが「どれだけお客様に寄り添った対応ができるか」です。「省人化はできたが、顧客満足度は下がった」では本末転倒ですので、人でなくても柔軟でスムーズな対応ができるか、という点に着目してAIの応答内容や対応プロセスを細かく検証しました。
その結果、AIでも一定の条件下でお客様のニーズに適切に応えられることが確認でき、AIによる対応がオペレーターの補完的な役割として機能することで、業務全体の効率化も期待できることがわかりました。
コミュニケーション推進部 寺木様
原:
我々事務本部では、日常業務で膨大なExcelマクロを活用しており、プログラミングの知識が十分でない方にとっては、ハードルが高い状況でした。そこで生成AIを活用することで、プログラム作成や保守管理のサポートが可能かどうかを検証しました。
私たちの業務で最も重要なのは「正確性」です。あらゆるタスクで100%の精度が求められる中で、生成AIがどこまでその精度に近づけるかを見極めることがテーマでした。結果として、AIが非常に高い精度でタスクを遂行できる場面もある一方で、人間による最終確認が不可欠なケースも明確になりました。これにより、AIと人の役割分担をより効果的に設計できるようになりました。
事務企画部 原様
ー プロジェクトの企画・推進を担ったデジタル企画部のお二人は、成果についてどのように感じていますか?
道家:
生成AI活用を「広く浅く」から「より深く」へとシフトするという観点では、当初の期待以上の成果が得られたと感じています。各部署の社員が自らの業務課題に向き合い、具体的なユースケースを考え検証したことで、今後のAI活用に向けた具体的なイメージが湧いたのではないかと思います。
白滝:
社内の至る所で、AIを業務に取り入れることに対する心理的ハードルが下がってきているのを実感しています。AIを「机上の空論」ではなく、業務の一部として受け入れる文化が醸成されつつあります。
AVILENの良かったところ
ー AVILENの支援についてどのように評価していますか?
道家:
最も期待していた部分としては、最新のAI技術に関する知見の共有と専門的なアドバイスでした。その点に関しては十分に支援していただきましたし、曖昧な課題や相談も丁寧に拾い上げ、具体的なアンサーをいただけたのが心強かったです。
また、単なるアドバイザーではなく、我々と共に走ってくれるパートナーであると感じました。多い時は2時間のセッションを週に2回、さらに我々事務局とのミーティングや裏側でのやりとりなど、かなりの時間を費やしていただいて大変有り難かったです。どのセッション、ミーティングでも全力投球する高橋社長の熱量の高さも印象的でした。
寺木:
参加した社員はおそらく、AI活用への期待値は大きくあるものの、どこまで可能でどこからが難しいのかは分からない、という人が多かったのではないかと思います。プロジェクトを進める中で、AIの可能性や課題について具体的な知見を共有していただけたことで、これから力を入れていくべき方向性が見えたのが良かったと考えています。
原:
生成AIをどう社内に普及させていくのかについての知見もいただけたのが良かったです。プロジェクトに参加したメンバーが、各部署に何を持ち帰って、どう広めていくかも非常に重要だと思います。
私も自身の部署や参加拠点で、本プロジェクトの取り組み内容や生成AIについて得た知見を共有したりして、生成AIに対してちゃんと理解してくれる人が増えたんじゃないかと思っています。彼らから「この業務に取り入れてみてはどうか」「こういう使い方はできないか」といった意見も出るようになってきて、プロジェクトに参加していないメンバーにも好影響が出てきています。
三菱UFJニコスのカルチャー
ー 僭越ながら、御社には「AIをはじめとした技術と向き合う」「現状に満足せず新しい挑戦をする」といった姿勢を強く感じます。そのカルチャーはどのように醸成しているのでしょうか?
白滝:
当社社長の角田やデジタル企画部担当の安田が「デジタル技術を活用して業務を変えていく」というトップメッセージを全社に発信していることが大きいと思います。そうしたトップの示すビジョン・姿勢が各部門にまで浸透しているのは感じますね。
さらに今回参加したメンバーたちは、技術活用や業務変革に対して非常に意欲的で、かつ「AIは魔法の杖ではない」ことを理解している人が多かったのが、プロジェクトがうまく進んだ大きな理由だと思います。
原:
部署・チームごとのボトムアップの取り組みも活発です。先ほど話したように生成AIの活用アイデアがメンバーから出てきたり、DXやAI活用に関する教育・人材育成を各チームが能動的に行っていたりしています。そういった場面が多くみられるので、トップダウンとボトムアップのバランスが非常に良い組織だなと感じます。
今後の展望
ー 変革のためには、これから入ってくる方の力も重要になるかと思いますが、必要としている人物像はありますか?
道家:
デジタル企画部は組織のDXを推進していく部署ですので、新しいものに抵抗がなく、むしろ楽しんで取り入れていくマインドを持った方が良いと思います。今いるメンバーの人達も、そういったタイプの人が多いですね。
寺木:
取り組みたいことがある、取り組むべきことに前向きになれる人が、一緒に働いてて楽しいです。一筋縄ではいかない場合や制限が多い場合も、どうしたらいいかをポジティブに考えられるかが大事だと思います。
原:
私の所属する事務企画部のグループは、AI活用といった前向きな施策を考える一方で、全社のリスク管理もしています。「変革」と「保守」、両方の側面を持つグループですので、複数の視点から物事を見られる人、フラットな立場で考えられる人が合っていると思います。
ー それぞれの部署の、今後のAI活用・DXにおける展望をお聞かせください。
寺木:
このプロジェクトで得た知見を踏まえ、今後はコールセンター業務におけるAI活用をさらに深化させていきたいです。お客様自ら、疑問をスピーディーに自己完結できる未来を目指し、顧客満足度の向上と業務効率化の両立に取り組んでいきます。
原:
AIを単なるツールとしてではなく、業務の中核に据えていくことが重要です。今後は、AIの活用範囲を拡大し、業務プロセス全体の最適化を図るとともに、社員一人ひとりがAIを使いこなせるスキルを身につけることを目指していきます。
白滝:
我々の事業に限らず、AIやデジタル技術は事業を進化させていく、生き残っていく上で欠かせない武器になります。あらゆる業務で効果的な使い方を模索し、組織を筋肉質な体制にしていくことが至上命題であり、それをデジタル企画部が引っ張っていきたいと考えています。
ー AVILENも引き続き全力で伴走させていただきます。インタビューにご協力いただきありがとうございました。
(インタビュアー:株式会社AVILEN 代表取締役 高橋光太郎)
記事の筆者
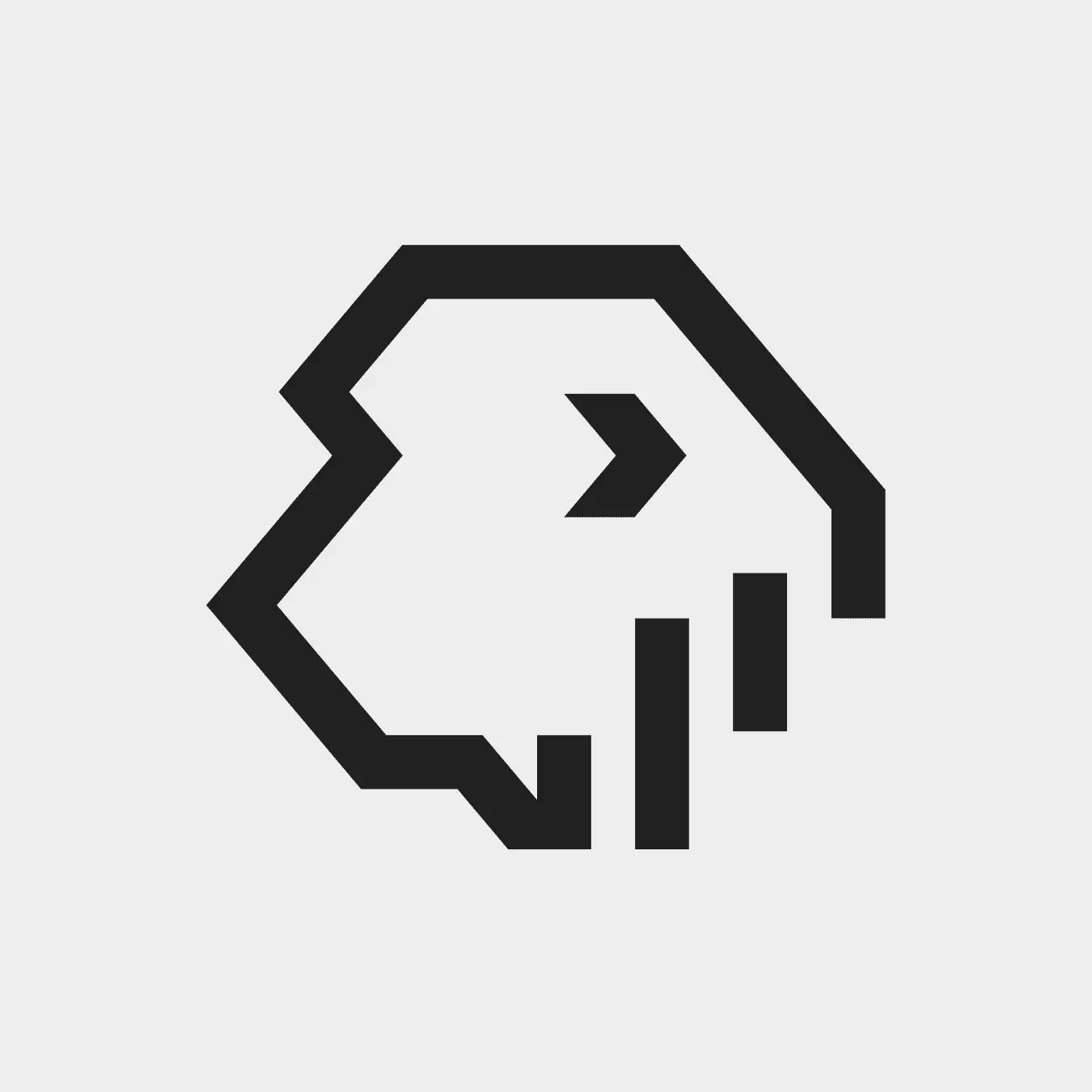
AVILEN編集部
株式会社AVILEN